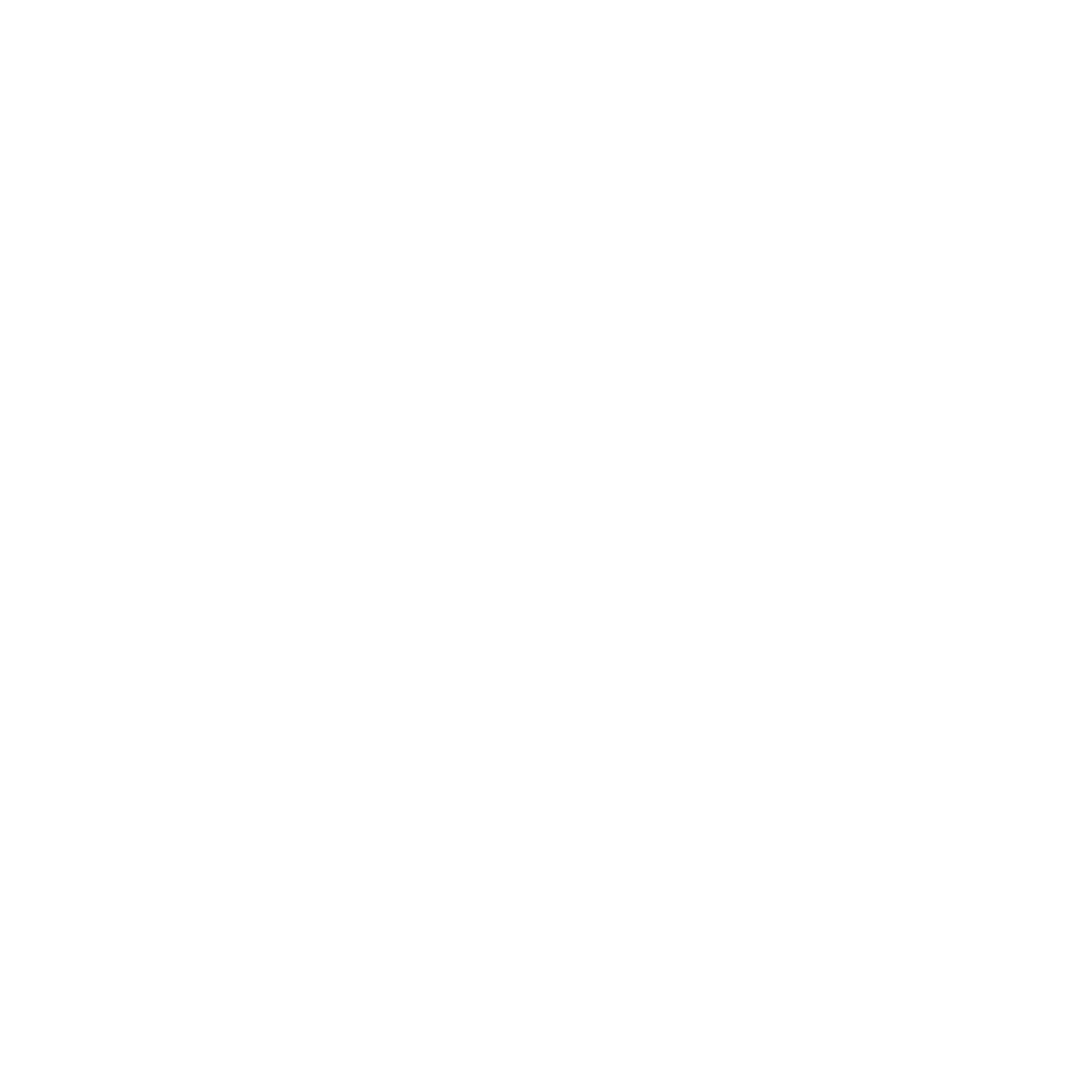競馬には安全確保のためにルールがある。例えば前の馬の先方に入るときは、2馬身以上の間隔を確保すること。突然斜めに走り出さないこと。さかのぼること戦前、こうした不正の監視は人間の知覚に依るところが大きかった。走路監視委員が双眼鏡で走る馬の様子を追い、不審な点を確認していたのだ。しかし、出走頭数が多いときや、同じ毛色の馬が多いときには、誤認も少なくなかったという。人間の目よりも正確な監視方法を模索して、映像記録の手法が検討されたが、効果的な運用は困難だった。当時の技術では現像に1週間もの時間を要したからだ。その様子を見るたびに、当時社長の山口𠮷久は思った。この問題を山口シネマで解決できないだろうか。決勝写真業務が軌道に乗りはじめた1951年頃のことだった。山口𠮷久には確信があった。戦前から培ってきた映画会社のノウハウと、フォトチャートカメラ開発で得た競馬の知識。このふたつを活用すれば、競走監視業務を軌道に乗せられるはずだ。
1953年、山口シネマによる競走監視業務が中山競馬場で正式採用された。映画撮影用の16ミリカメラで撮影し、現像する。今までとの大きな違いは、競馬場内の暗室で現像を行うこと。現像時間を短縮するうえでネックとなったのは、フィルムの乾燥だった。考え出したのが、木枠に巻きつけたフィルムを現像タンクに入れ、次に乾燥器にかける方法。これは映画会社の技法を発展させたもので、長いフィルムを広げることにより、乾きを早めるというしくみだ。現代の目で見ればシンプルな手工業だが、なんと現像時間を一時間半に短縮するという成果を上げた。1955年、この手法は “ドラム式”でさらなる発展を遂げる。これは記録映画会社のカメラマンをしていた社員の発案だった。木製の筒=ドラムにフィルムを巻きつけ、モーターで回転させながら、まんべんなく熱風を当てる。すると、一時間半の現像時間が、30分程度に、見たい箇所だけの現像であれば15分まで短縮されたのだった。撮影から現像まで1週間を要していた頃から、わずか5年のうちに果たした進化だった。山口シネマは誇りをもってこのフィルムを、日本ではじめて「パトロールフィルム」と呼んだ。
ドラム式16ミリフィルム現像法
1956年から開始した民放局による競馬中継テレビ放送の影響や、いざなぎ景気と呼ばれる好況を受けて、競馬場の観客数は増加の一途をたどっていた。同時に、スタンドが増改築され、レースが見えにくいと感じるファンも増えていた。肉眼で見えないものを捉えるのは、映像の大きな使命だ。そう考えた山口𠮷久は新たな挑戦を決断した、すなわち“テレビをやろう”。当時、テレビの受診契約は100万件を越え、普及浸透の一歩を踏み出していた。彼も時代の新しい風を敏感に感じ取っていたのだ。競馬場でテレビ放送を流す。この目標に向かって、山口シネマは一気呵成に走り出した。「山口シネマさんは映画屋さんでしょう。テレビができるんですか」競馬場へ営業活動をしていたとき、山口𠮷久はそう言われたことがある。確かにフォトチャートカメラやパトロールフィルムと違って、競合の多い業界だ。カメラや受信機の開発力では勝てるとは言い切れない。しかし、これまでも競馬の映像を撮り、その映像を撮るための機器や装置を自分たちで開発してきたのだ。「できます」と山口𠮷久は決意をもってうなずいた。
当時、まだ得体の知れないテレビというもののために、あらかじめケーブルを整備した競馬場は一カ所もなかった。山口シネマは、配線作業から着手する必要があった。テレビカメラの受信機メーカーと協力し、図面を引いて、特注のケーブルを配置していく。未踏の開拓地を前に、ひるむことはなかった。「山口さん、困りますよ。勝手に改造されちゃ」工業用カメラでテスト撮影を繰り返していた頃、製造元の電機メーカーから苦情の声が上がった。確かに、工業用カメラは標準レンズと望遠レンズの2連装式へと大幅な改造が加えられていた。山口𠮷久は説得する。「ファンが映像を見るとき、何を一番知りたがると思いますか。ゼッケンの馬番号です。ファンサービス放送をする以上、あの番号がはっきり写らないと意味がないんです」その言葉に込められた、ただならぬ熱意に心動かされ、電機メーカーの社員は場内テレビへの協力を約束した。1962年、ついに山口シネマは場内テレビの試験放送にこぎ着けた。テレビの前には人だかりが生まれ、その反響は凄まじいものだった。
当時の中山競馬場の場内テレビ